その理由を解説します。
コミュニケーション能力とは何か?
まず、ここで指している「コミュニケーション能力」とは何か。一般的にはコミュ力が高い人はこういうイメージがあるかと思います。
- よく喋る
- 明るい
- 声が通る
ですが、リモートワークではこれらはどっちでもいいことです。リモートワークで求められるコミュ力は「察する力」だからです。相手が求めていることを理解する力ともいいます。
例えば、友人を自宅に招いたとしましょう。友人が「暑くない?」と言いました。
ここでコミュ力のない人は「暑い(寒い)」と答えるだけ。コミュ力の高い人は相手の真意に気づく。だから「クーラーつけようか」というキャッチボールができる。
キャッチボールは、相手が投げたボールをキャッチして投げ返して初めて成立です。グローブからボールを落としたり、キャッチするだけでは成立していないのです。
察する力は、仕事・プライベートとどんな場面でも同じように発動します。丁寧か丁寧じゃないかという違いだけで、上司に対しても家族や恋人に対しても同じレベルで発動します。
察することができなければ、イメージを感覚で共有することはできません。となると、イメージを言語化して説明する必要が出てくるわけです。ある程度の言語化は可能だとしても、すべてを言葉に置き換えるのは始めから無理な話です。絵画を言葉で説明可能ですか?
そういう話なので、察することができない人は実質的に高次元の仕事は不可能という話になるのです。
察する力がない人に任せられるのは、答えが1つと決まっているマニュアル作業だけです。それって、プログラムに代替できてしまう可能性が高いんですよね。
距離があるからこそ、コミュ力が求められる。
リモートワークは同じ空間で時間を共有する機会が減ります。無用なストレスを生みにくいメリットもありますが、物理的心理的な距離も生まれやすいのです。
ゆえに、察する力がない(相手の真意を掴むのが下手)と思う人は、積極的にコミュニケーションに参加していかないと建設的なキャッチボールが生まれてきません。
ただ、一番の問題は、察する力がない人には自覚がないことです。だから、自ら振り返ってリモートワークに適応することもできないのです。「自分は当てはまってないか」と少しでも自省する人は、すでに察する力があるのです。だから、この記事自体も何の役に立たないという話です。
それでも私が伝えたいのは「相手の真意を掴むことがリモートワークを円滑にする」ということです。












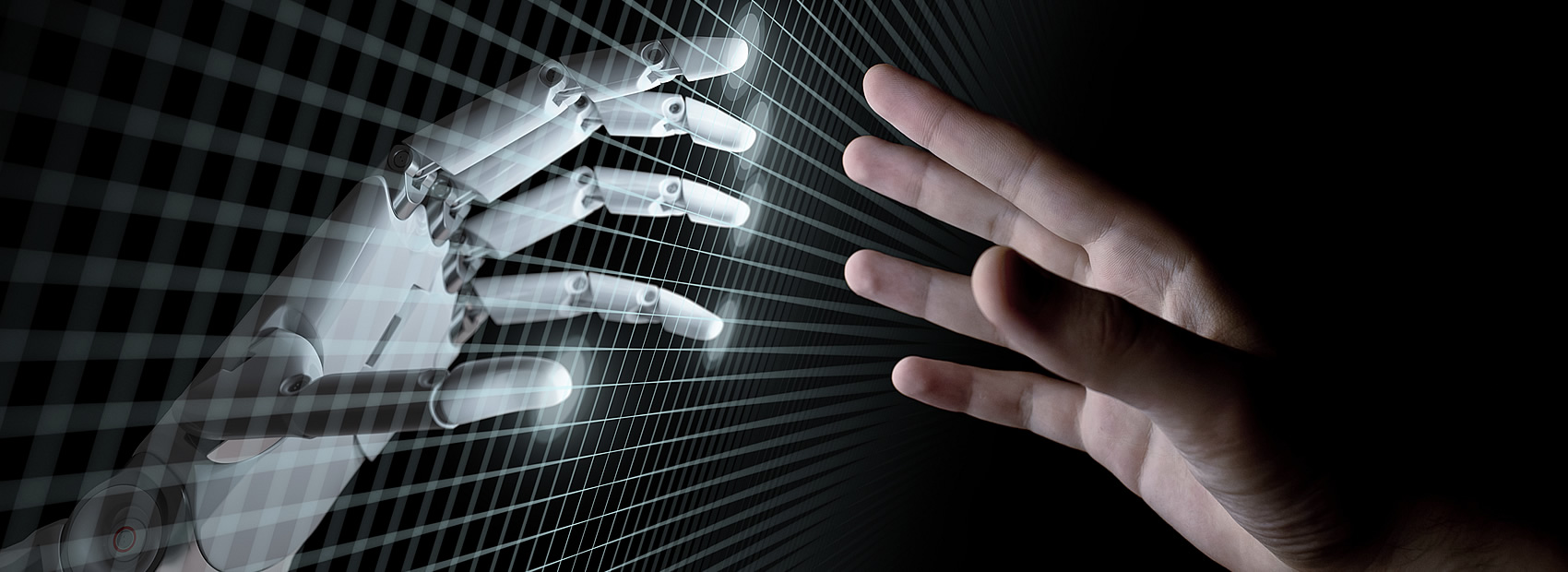


















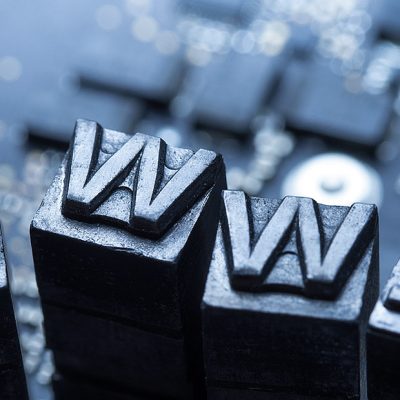
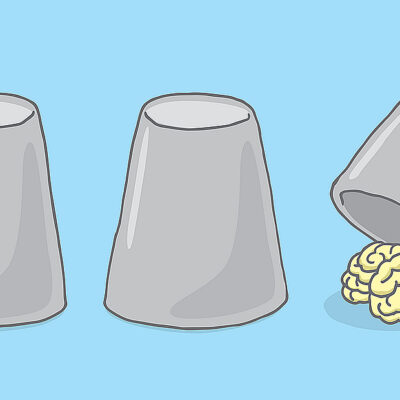






この記事へのコメントはありません。