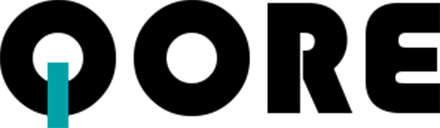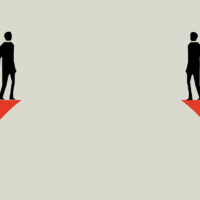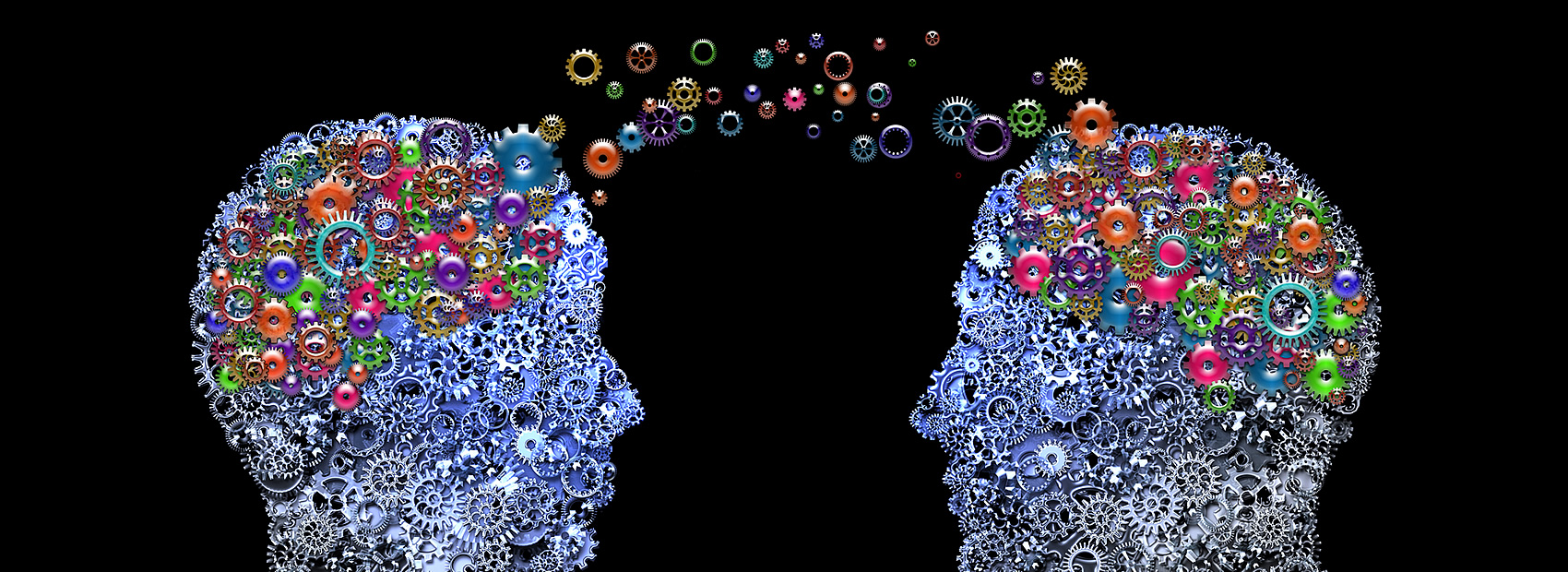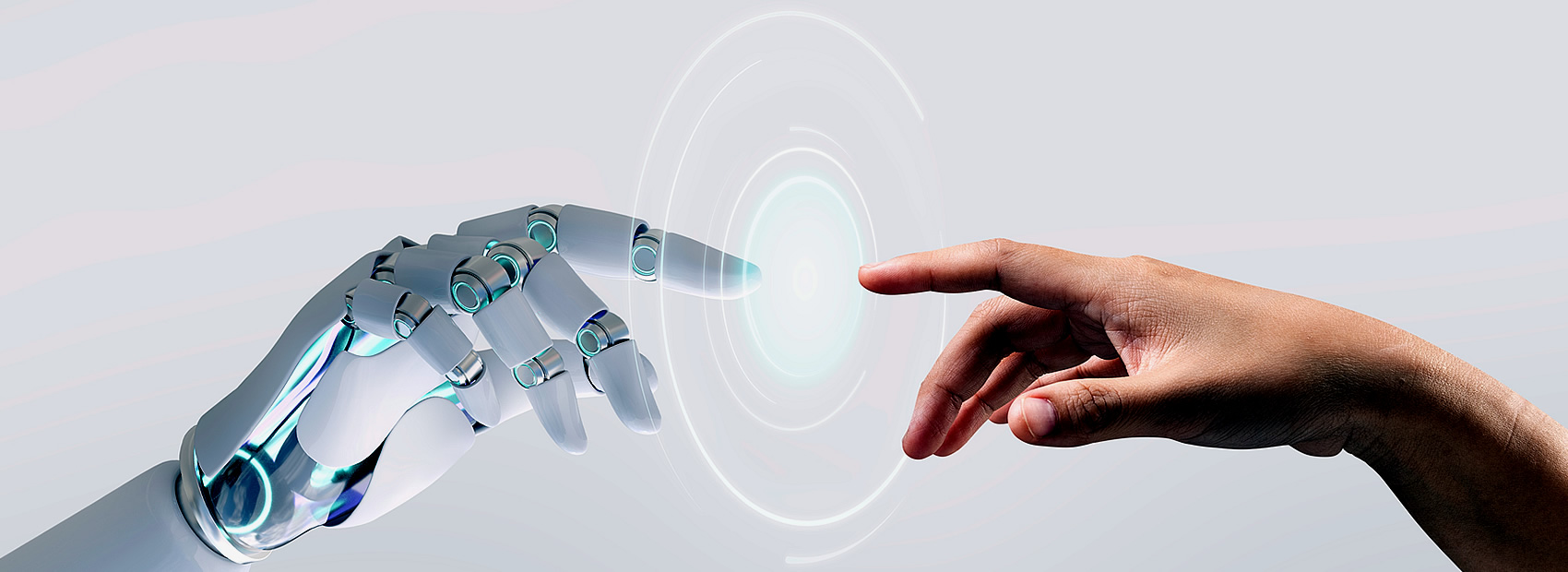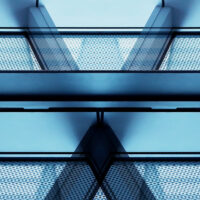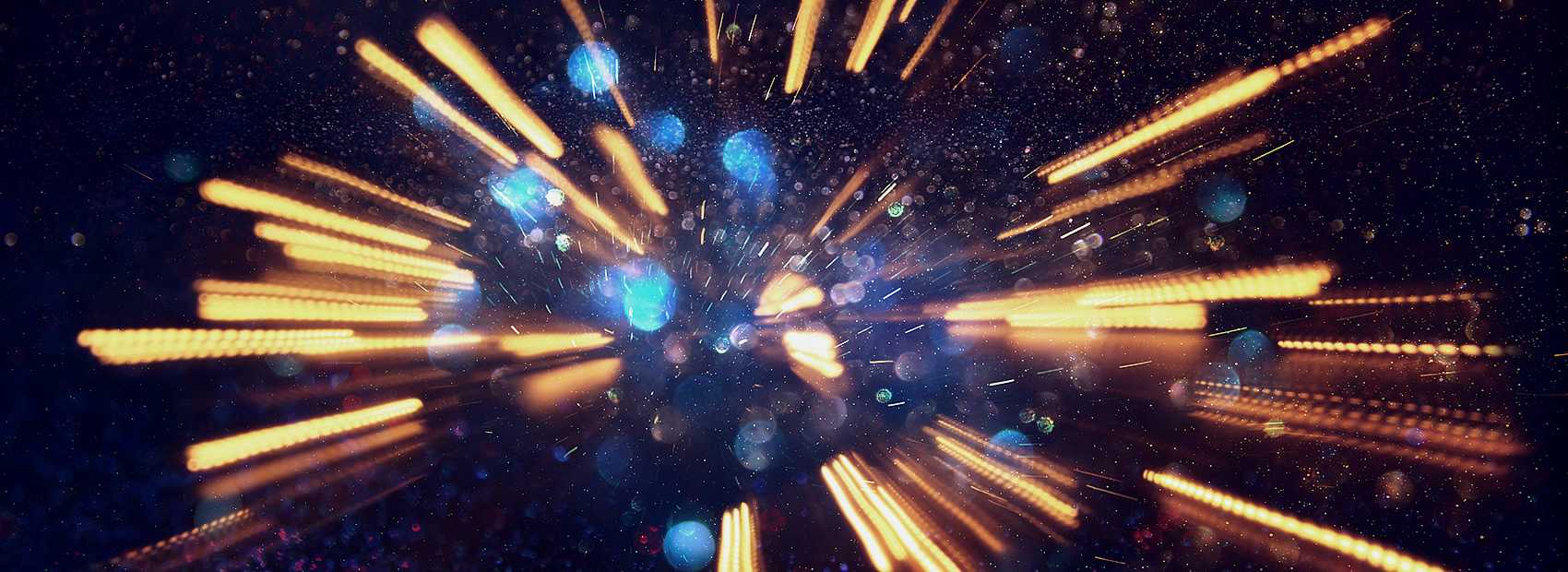「創造的破壊」とは何か?
創造的破壊(そうぞうてきはかい、英語: Creative destruction)とはヨーゼフ・シュンペーターの著書『資本主義・社会主義・民主主義』の第7章で提唱された経済学用語の一つである。経済発展というのは新たな効率的な方法が生み出されれば、それと同時に古い非効率的な方法は駆逐されていくという、その一連の新陳代謝を指す。
創造的破壊はマクロな意味ではそうなりますが、もっとクリエイター目線で見ていくと「自己否定」ではないかと思います。
自分の過去の作品を否定し、刷新していく行為。これを繰り返していなければクリエイター個人として磨かれていきません。
前例踏襲型の”クリエイター”は、過去の作品と比較しても成長がないものです。一度fixしたもの(仕様・マニュアル等)は上書きされない。自身の気づきによって疑いを持つに至らない。
創造的破壊は自分の過去の作品に疑いを持つことから始まります。
個人版「創造的破壊」のプロセス:
- 作品をつくる。
- 達成感が生まれる。
- 過去の作品を疑う。
- 精査する。
- 次の作品に活かす。
熱を籠めて制作したものは、到達した時点では「完璧」だと思っているかもしれない。ただ、そう思えるのは一時だけ。時が経てば「本当にこれでよかったのか?」と疑うようになる。そこから過去の作品を破壊する行為とともに、自分の新しい課題との直面が始まる。
とはいえ、「本当にこれでよかったのか?」と疑いを持てること自体が、その人の資質です。どういうことかというと、深い思考がなければ、疑いを持つことができないのです。浅い思考なら、過去の判断・決定プロセスを見直す必要がありません。何もないのですから。

深い海だから、人は探索する。
創造的破壊のプロセスを振り返りましょう。
個人版「創造的破壊」のプロセス:
- 作品をつくる。
- 達成感が生まれる。
- 過去の作品を疑う。
- 精査する。
- 次の作品に活かす。
3の「疑う」の実行には、深い思考が必要。しかし、深い思考を宿すには1の「作品をつくる。」が鍵になってくる。どういうことかというと、エネルギーを籠めているかどうかです。最高のものを生み出そうとする熱量によって神経細胞とシナプスが複雑に繋がっていき、思考が深くなっていく。
思考の深さが数メートルならば誰も探索はしないが(しても意味ない)、数百メートルの深さともなると本格的な探索が始まる。そういうイメージです。ですから、モノづくりにかける熱量が創造的破壊のプロセスには重要になってくるわけですね。
作品にぶつける熱量を持ちたい方は岡本太郎の「自分の中に毒を持て」を読むのが良いですね。